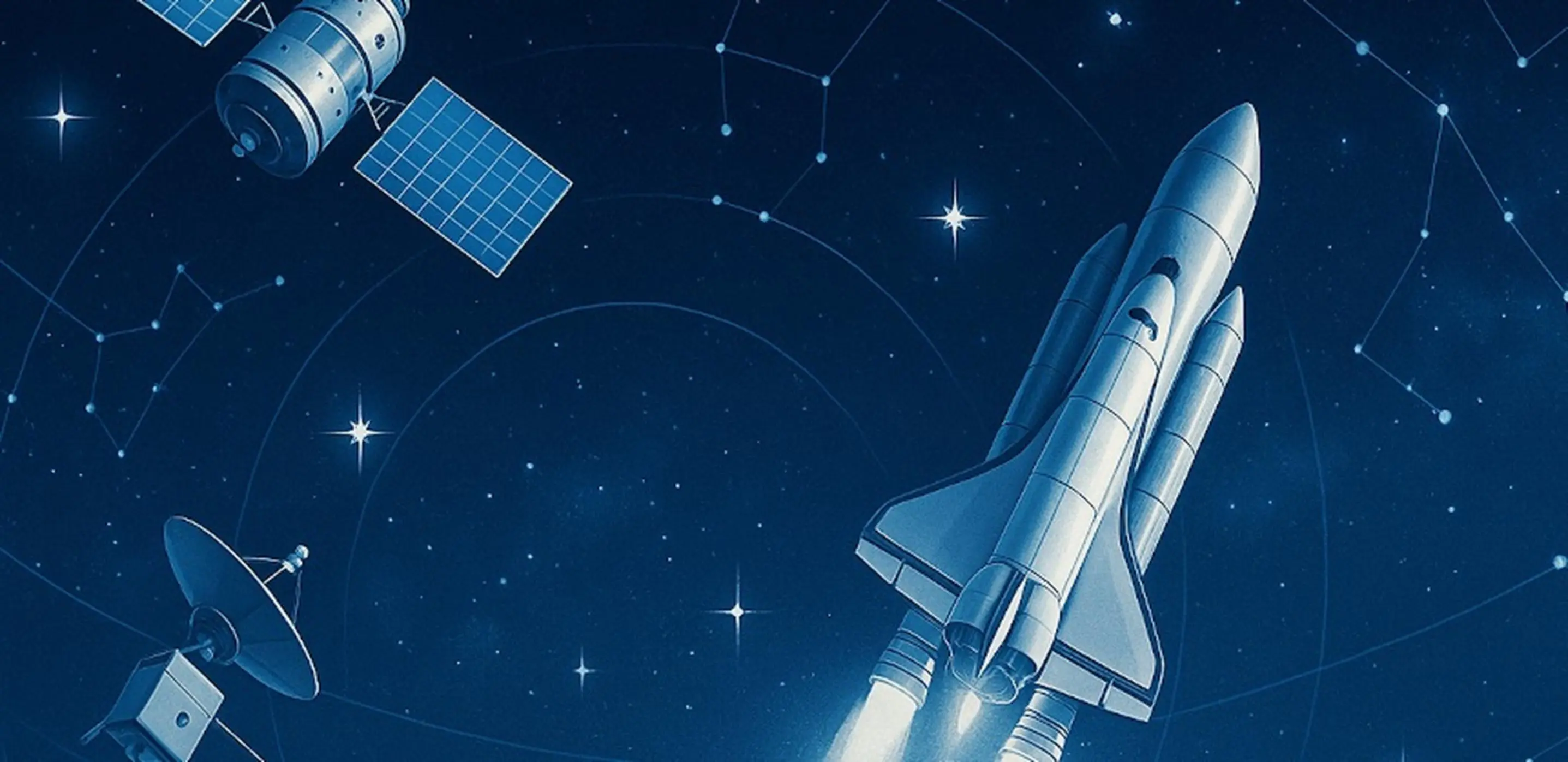太陽同期軌道
- よみがな: たいようどうききどう
- 英語名: Sun Synchronous Orbit
太陽同期軌道の概要
太陽同期軌道とは、地球を回りながら常に同じ太陽光の角度で地表を観測できるように設計された軌道である。
太陽同期軌道の詳細
太陽同期軌道は、地球周回軌道の一種で、衛星が地球を周回する際に、地表の同じ場所を毎回ほぼ同じ太陽光の条件下で観測できるようになっています。
これにより、時間による変化を正確に比較することが可能となり、気象観測や地形モニタリングなどに非常に有効です。
この軌道の特徴は、地球の自転や公転によって太陽の見かけの位置が変化する中でも、衛星の軌道面がその変化に合わせてわずかに歳差運動することにあります。
この調整には地球の扁平率(極がつぶれた形)が影響し、設計には高度な軌道力学が用いられます。
太陽同期軌道は通常、地球の極近くを通る「極軌道」に似た形状をしており、高度600〜800km付近に位置します。
観測対象が昼間の地球に限定されるという特徴があります。
太陽同期軌道とは、人工衛星が地球を周回する際に地表の同じ場所を毎回ほぼ同じ太陽光の条件下で観測できるように設計された軌道です。
極軌道において軌道の形状を工夫することにより、太陽の動きと衛星の動きが同期されるという意味合いを持ちます。
この特性により、時間による地表の変化を正確に比較することが可能となり、気象観測や地形モニタリング、環境変化の追跡などに非常に有効です。
太陽同期軌道の最大の特徴は、毎回ほぼ同じ時刻に同じ地域の上空を通過するという点にあります。
地球の自転や公転によって太陽の見かけの位置が変化することを考慮した上で、衛星の軌道面を工夫することにより、
太陽光の角度や影の状態が一定に保たれるのです。
これにより、観測データの比較や解析が非常にしやすくなります。
太陽同期軌道は、地球の北極や南極の近くを通る「極軌道」に分類されます。
そのため高度数百kmの低軌道ということになります。
この高度を用いる衛星は、1日に複数回地球を周回することにより地球全体を網羅的に観測することが可能です。
太陽同期軌道は地球観測衛星の多くに採用されています。
気候変動の監視、森林伐採の追跡、都市の拡大、氷河の融解など、さまざまな環境・地理的課題に対するデータ提供に貢献しています。
また、農業や災害対応、資源管理などの分野でも、太陽同期軌道を活用した衛星データが重要な役割を果たしています。
このように、太陽同期軌道は地球の変化を継続的かつ一貫した条件で観測するための理想的な軌道であり、現代の地球観測技術の中核を担う存在です。
もっと宇宙開発について知りたい方は、
以下の関連用語についてもチェックしましょう!
関連用語・トピック
他カテゴリの用語を見てみる
人気のページ
宇宙開発ナビ:宇宙開発をこれから学ぶ人たちへ
宇宙開発について初めて学ぶならまずはこのページから。
宇宙開発ナビ:宇宙開発のメリット・デメリット とは?
宇宙開発のメリットとデメリットについて、それぞれ整理して比較します。
宇宙開発ナビ:大気圏に物体が突入すると燃えるのはなぜ?
隕石や宇宙船が大気圏に突入する際に燃えるように見える理由について説明します。
宇宙開発ナビ:太陽フレアの影響 とは?
地球にも様々な影響を及ぼす太陽フレアについて、その原因から対策まで説明します。
宇宙開発ナビ:フライバイとスイングバイの違い とは?
宇宙開発のメリットとデメリットについて、それぞれ整理して比較します。
宇宙開発用語集:通信遅延 とは?
宇宙開発を行う上で避けては通れない「通信遅延」について、詳しく解説します。
宇宙開発用語集:打ち上げ失敗 とは?
ロケット打ち上げ中に発生するトラブルとその影響について紹介します。
宇宙開発用語集:軌道の用語一覧
「軌道」という宇宙特有の考え方について、わかりやすく説明しています