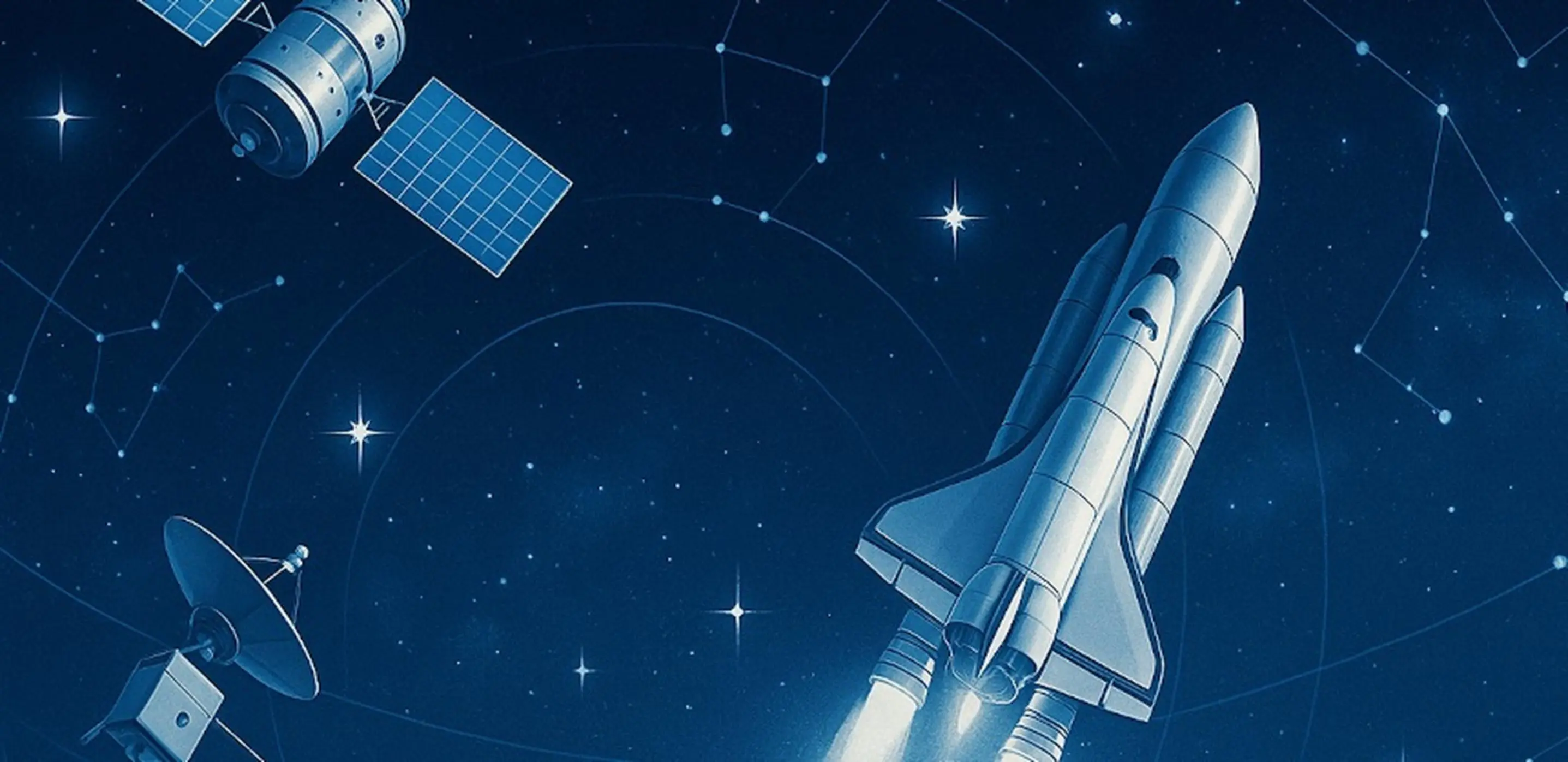極軌道
- よみがな: きょくきどう
- 英語名: Polar Orbit
極軌道の概要
極軌道とは、人工衛星が地球の南北を通過するように周回する軌道である。
極軌道の詳細
この軌道は、地球全体を網羅的に観測するのに適しており、地球観測衛星に広く利用されています。
衛星は高度約600〜800kmの低軌道を周回し、1日に複数回地球を一周することが可能です。
極軌道を用いることで、地球の全表面を定期的に観測できます。
そのため、気候変動の監視や災害対応、環境調査などに活用されています。
また、極軌道の中でも特に特殊な軌道として太陽同期軌道があります。
太陽同期軌道は、常に同じ太陽光条件下での観測を可能とするもので、データの比較や解析が容易になります。
極軌道は、地球全体を対象とする科学的・技術的な観測において、非常に重要な役割を果たしています。
極軌道とは、人工衛星が地球の極地、つまり北極と南極を通過するように設計された軌道のことを指します。
「衛星が地球を回る」というと、多くの場合は赤道上空を飛行する様子をイメージするかもしれませんが、
極軌道は逆に赤道を横切って飛行する軌道です。
衛星が地球の南北方向に周回するこの軌道は、地球全体を均等に観測するのに非常に適しています。
というのも、極軌道は毎回同じ場所の上空を通過するわけではないからです。
一周するたびに地球が自転する動きに合わせて少しずつ通過する位置をずらすことで、毎回異なる地域の上空を通過することになります。
その結果、地球全体を網羅的に観測することが可能となるのです。
このような特徴から、極軌道は地球観測衛星に広く利用されています。
衛星は高度数百kmの低軌道を周回することで、1日に10回以上地球を一周することも可能です。
例えば国際宇宙ステーションの軌道は高度400kmの極軌道であり、90分で地球を一周します。
つまり、1日に16回地球を回ることになります。
このような手法を用いることで、短期間の間に広範囲のデータを収集することができ、
地球の変化をリアルタイムに近い形で把握することができるようになるのです。
地球の全表面を定期的に観測することができるという利点から、極軌道はさまざまな分野で活用されています。
地球の様子を空から監視するリモートセンシングが近年広まっていますが、それに用いられる衛星は大抵低軌道・極軌道の衛星です。
特に環境分野においては、気候変動の長期的な監視や森林伐採や都市化の進行状況の把握、海洋の温度や氷河の融解状況の調査などに役立てられています。
この他にも防災の分野では、洪水や地震・山林火災などの自然災害に対して迅速な対応をするための情報を提供する重要な役割を果たしています。
ところで、極軌道の中でも特に重要な軌道として「太陽同期軌道」があります。
これは、衛星が地球を周回する際に、常に同じ太陽光条件下で地表を観測できるように設計された軌道です。
つまり、衛星が通過する時間帯が毎日ほぼ同じになるため、地表の影の状態や光の反射などが一定となり、観測データの比較や解析が非常にしやすくなります。
これにより、長期的な変化の検出や精密な地表解析が可能となります。
このように、極軌道は地球全体を対象とする科学的・技術的な観測において欠かすことのできない軌道です。
地球環境の理解を深め、持続可能な社会の実現に向けた基盤を支える役割を果たしています。
もっと宇宙開発について知りたい方は、
以下の関連用語についてもチェックしましょう!
関連用語・トピック
他カテゴリの用語を見てみる
人気のページ
宇宙開発ナビ:宇宙開発をこれから学ぶ人たちへ
宇宙開発について初めて学ぶならまずはこのページから。
宇宙開発ナビ:宇宙開発のメリット・デメリット とは?
宇宙開発のメリットとデメリットについて、それぞれ整理して比較します。
宇宙開発ナビ:大気圏に物体が突入すると燃えるのはなぜ?
隕石や宇宙船が大気圏に突入する際に燃えるように見える理由について説明します。
宇宙開発ナビ:太陽フレアの影響 とは?
地球にも様々な影響を及ぼす太陽フレアについて、その原因から対策まで説明します。
宇宙開発ナビ:フライバイとスイングバイの違い とは?
宇宙開発のメリットとデメリットについて、それぞれ整理して比較します。
宇宙開発用語集:通信遅延 とは?
宇宙開発を行う上で避けては通れない「通信遅延」について、詳しく解説します。
宇宙開発用語集:打ち上げ失敗 とは?
ロケット打ち上げ中に発生するトラブルとその影響について紹介します。
宇宙開発用語集:軌道の用語一覧
「軌道」という宇宙特有の考え方について、わかりやすく説明しています