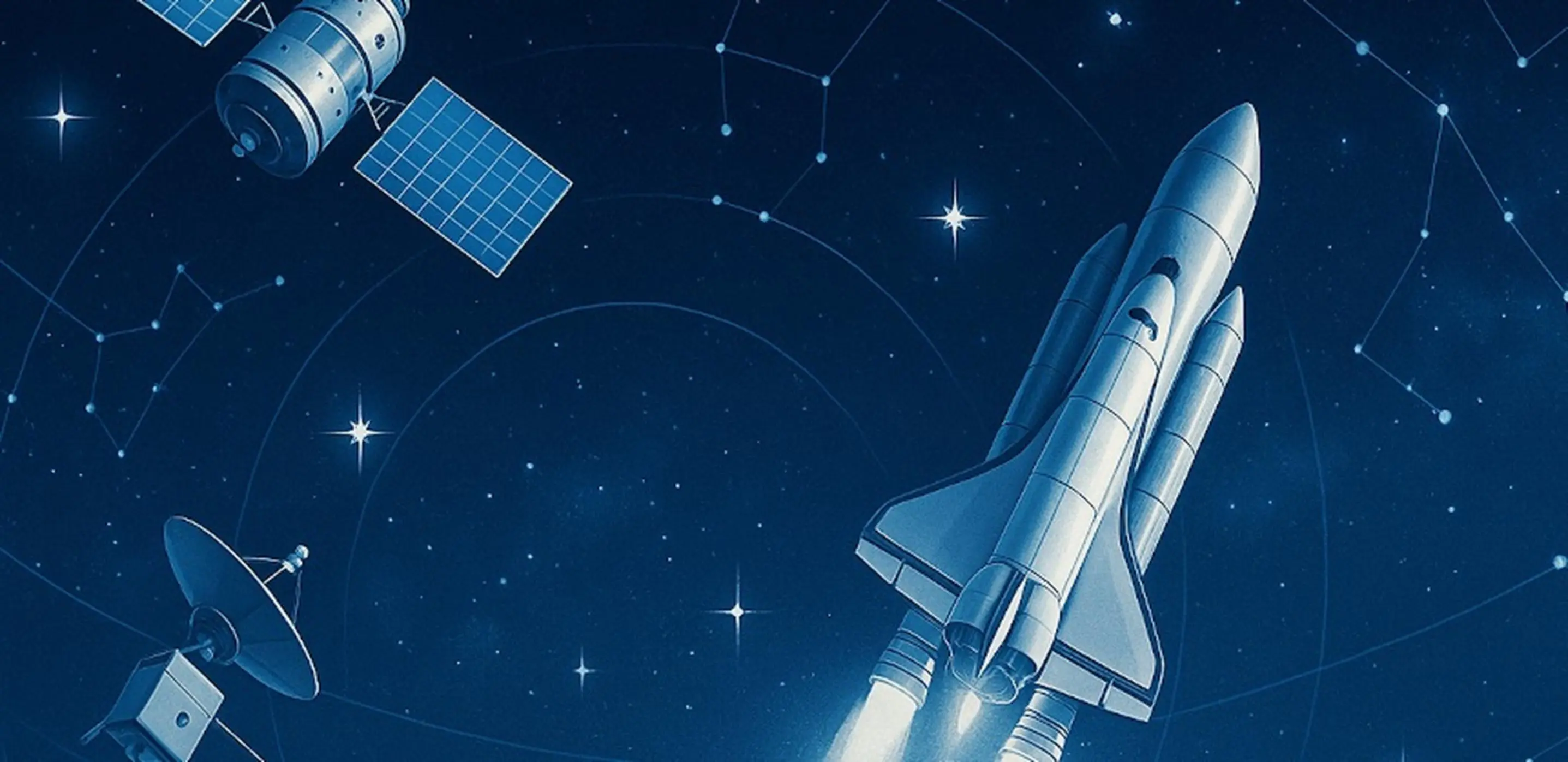低軌道
- よみがな: ていきどう
- 英語名: Low Earth Orbit
低軌道の概要
低軌道とは、地上からおおよそ高度200km〜2,000kmの範囲に位置する人工衛星の軌道のことである。
低軌道の詳細
低軌道(LEO)とは、地球の大気圏のすぐ外側に位置する、高度約200〜2,000kmの範囲にある人工衛星の軌道を指します。
この軌道は地球に比較的近いため、衛星からの観測や通信が高精度で行えるという利点があります。
そのため、地球観測衛星や通信衛星、さらには国際宇宙ステーション(ISS)など、多くの人工衛星がこの軌道を利用しています。
低軌道の最大の特徴の一つは、打ち上げコストを低く抑えられるという点です。
これは、高度が低く打ち上げに求められるエネルギーが低くなることから、ロケットの燃料消費が少なく済むことに起因しています。
これにより、近年では民間企業による低軌道衛星打ち上げも活発になっており、宇宙開発の裾野が広がっています。
一方で、LEOにはいくつかの課題も存在します。その一つが、大気の影響です。
低軌道は地球に近い分、空気がわずかながら残っているのです。
すると、低軌道を飛行する衛星は空気抵抗を受けることになります。
それは小さな力ですが、長時間航行しているとエネルギーのロスが蓄積して地球へと落下してしまうのです。
そのため、長期間の運用には定期的な軌道修正が必要となります。
軌道修正には当然ながら燃料の消費が必要となることから、この点は衛星の寿命にも影響を与える要因となるのです。
また、低軌道はスペースデブリ(宇宙ごみ)の密集地帯としても知られています。
過去に打ち上げられた衛星やロケットの破片などが多数漂っており、新たな衛星の打ち上げや運用において衝突のリスクが高まっています。
このため、衛星の衝突回避や軌道上の物体の監視・管理は、宇宙開発における重要な課題となっています。
それでもなお、低軌道は地球に近いという利点を活かして多くの場面で活用されています。
宇宙ごみが多いというのは、裏を返せばそれだけこの軌道がこれまでに数多く使われてきたという証左でもあるのです。
実際に、気象観測、災害監視、インターネット通信、教育・研究など、さまざまな分野で活用されています。
今後も技術の進歩とともに、より安全で効率的な低軌道の利用が求められていくでしょう。
もっと宇宙開発について知りたい方は、
以下の関連用語についてもチェックしましょう!
関連用語・トピック
他カテゴリの用語を見てみる
人気のページ
宇宙開発ナビ:宇宙開発をこれから学ぶ人たちへ
宇宙開発について初めて学ぶならまずはこのページから。
宇宙開発ナビ:宇宙開発のメリット・デメリット とは?
宇宙開発のメリットとデメリットについて、それぞれ整理して比較します。
宇宙開発ナビ:大気圏に物体が突入すると燃えるのはなぜ?
隕石や宇宙船が大気圏に突入する際に燃えるように見える理由について説明します。
宇宙開発ナビ:太陽フレアの影響 とは?
地球にも様々な影響を及ぼす太陽フレアについて、その原因から対策まで説明します。
宇宙開発ナビ:フライバイとスイングバイの違い とは?
宇宙開発のメリットとデメリットについて、それぞれ整理して比較します。
宇宙開発用語集:通信遅延 とは?
宇宙開発を行う上で避けては通れない「通信遅延」について、詳しく解説します。
宇宙開発用語集:打ち上げ失敗 とは?
ロケット打ち上げ中に発生するトラブルとその影響について紹介します。
宇宙開発用語集:軌道の用語一覧
「軌道」という宇宙特有の考え方について、わかりやすく説明しています