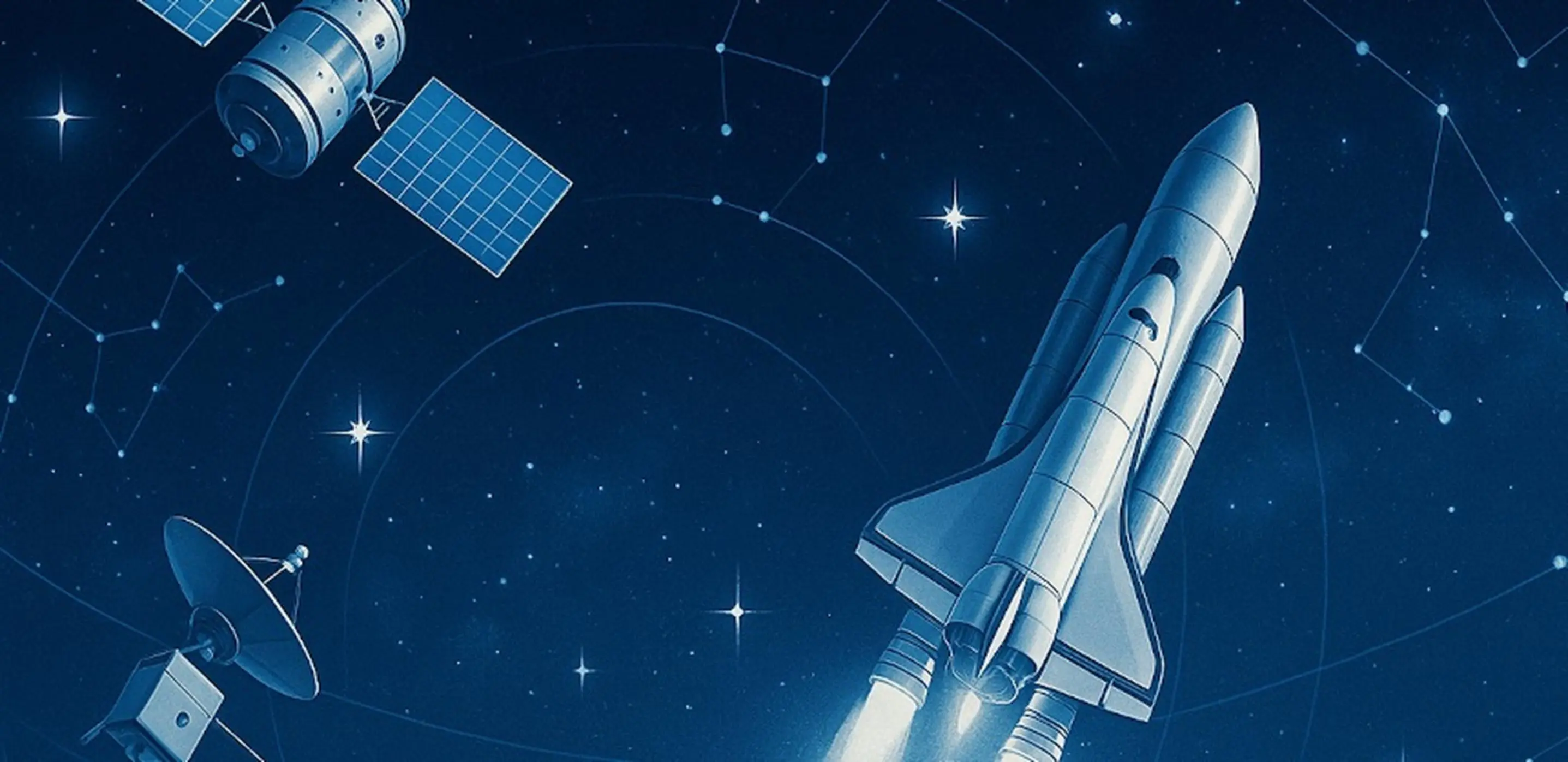大気圏に物体が突入すると燃えるのはなぜ?
「大気圏に物体が突入すると燃える」という現象は、ニュースや映画などでよく目にします。
しかし、その理由について正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
このページでは、「なぜ燃えるのか?」という疑問に対して、大気圏の仕組みや宇宙空間との違いを踏まえながら、わかりやすく解説していきます。
結論:大気圏に物が突入すると、空気が圧縮されて熱と光が発生する!燃えているわけではない!
宇宙空間から地球に戻ってくる物体が「燃える」ように見えるのは、高速で大気圏に突入してくる物体によって空気が一気に圧縮されるためです。
これは実際には「燃焼」ではなく、「発熱・発光」と言った方が正確です。
物体が空気を押しのけながら高速で移動することで、空気が圧縮されて高温になり、物体の表面が熱せられるのです。
そもそも大気圏 とは?
大気圏とは、地球を取り巻く空気の層のことです。
地表から高度約1000kmまで広がっており、主に対流圏・成層圏・中間圏・熱圏・外気圏の5つの層に分かれています。
高度が上がるにつれて空気は薄くなり、宇宙空間との境界は明確ではありませんが、一般的には高度100km付近が宇宙との境目とされています。
この空気の層があることで、地球は生命を育む環境を保っています。
大気圏の詳しい説明についてはこちら
大気圏に物が突入するとどうなる?
宇宙空間では空気がほとんど存在しないため、物体は抵抗なく移動できます。
しかし、大気圏に突入すると、急激に空気の密度が高くなり、物体は猛烈な空気抵抗を受けます。
このとき、空気が圧縮されることによって物体の表面温度は数千度にも達し、光を放つようになります。
この現象が「燃えている」ように見えるのです。
再突入の詳しい説明についてはこちら
実際に大気圏に突入した様子を見るには?
実際の大気圏突入の様子は、宇宙船の帰還映像や人工衛星の落下映像などで見ることができます。
また、夜空に見える「流れ星」も、宇宙から飛来した微小な物体(隕石など)が大気圏に突入して発光している現象です。
流れ星は秒速数十km/sという高速で突入するため、短時間で明るく光って消えてしまいます。
小惑星探査機はやぶさが地球に帰還した際の映像はこちら
大気圏に再突入する宇宙船のための対策 とは?
宇宙船が地球に帰還する際には、表面が高温になることを想定して「耐熱シールド」が装備されています。
このシールドは、熱を吸収・放出することで内部の乗員や機器を守ります。
スペースシャトルやカプセル型の帰還船には、耐熱タイルやアブレータ(熱で削れて熱を逃がす素材)などが使われています。
これらの技術により、安全に地球へ戻ることが可能になっています。
耐熱シールドの詳しい説明についてはこちら
もっと大気圏再突入について知りたい人へ
信頼できるページの記事を読むことで、宇宙船の再突入や大気圏突入の仕組みについてより深く理解できます。
こちらのページでは、JAXAの有人部門によって大気圏再突入時に熱が発生する理由についての解説がなされています。
また、ファン!ファン!JAXA!では大気圏についての詳しい説明を見ることができます。
さらに、大気圏再突入を前提として設計された耐熱カプセルに関する話を読むことによって、理解が深まるでしょう。
また、宇宙開発用語集でも、大気圏や再突入に関する様々な用語を解説しています。 詳細は以下の関連用語のページから見てみてください。
宇宙環境に関する用語の意味の一覧はこちら
まとめ
- 宇宙から地球に戻る物体が「燃える」のは、空気との摩擦や圧縮によって高温になり、光を放つため。
- 大気圏とは地球を取り巻く空気の層で、宇宙との境界は高度約100km。
- 宇宙船は耐熱シールドなどの技術で高温から守られている。
🚀 宇宙開発ナビでは、宇宙に関する疑問にわかりやすく答える記事を随時更新しています。
今後も宇宙についてもっと知りたい方は、ぜひブックマークをお願いします!
宇宙開発用語集のおすすめページ
宇宙開発ナビのおすすめページ
- 宇宙開発のメリット・デメリット とは?
- 宇宙線と放射線の違い とは?
- 「宇宙は無重力ではない」とはどういうこと?
- 人工衛星は衝突しないのか?
- 太陽フレアの影響 とは?
- 宇宙開発ナビーこれから宇宙を学ぶ人のために
人気のページ
宇宙開発ナビ:宇宙開発をこれから学ぶ人たちへ
宇宙開発について初めて学ぶならまずはこのページから。
宇宙開発ナビ:宇宙開発のメリット・デメリット とは?
宇宙開発のメリットとデメリットについて、それぞれ整理して比較します。
宇宙開発ナビ:大気圏に物体が突入すると燃えるのはなぜ?
隕石や宇宙船が大気圏に突入する際に燃えるように見える理由について説明します。
宇宙開発ナビ:太陽フレアの影響 とは?
地球にも様々な影響を及ぼす太陽フレアについて、その原因から対策まで説明します。
宇宙開発ナビ:フライバイとスイングバイの違い とは?
宇宙開発のメリットとデメリットについて、それぞれ整理して比較します。
宇宙開発用語集:通信遅延 とは?
宇宙開発を行う上で避けては通れない「通信遅延」について、詳しく解説します。
宇宙開発用語集:打ち上げ失敗 とは?
ロケット打ち上げ中に発生するトラブルとその影響について紹介します。
宇宙開発用語集:軌道の用語一覧
「軌道」という宇宙特有の考え方について、わかりやすく説明しています