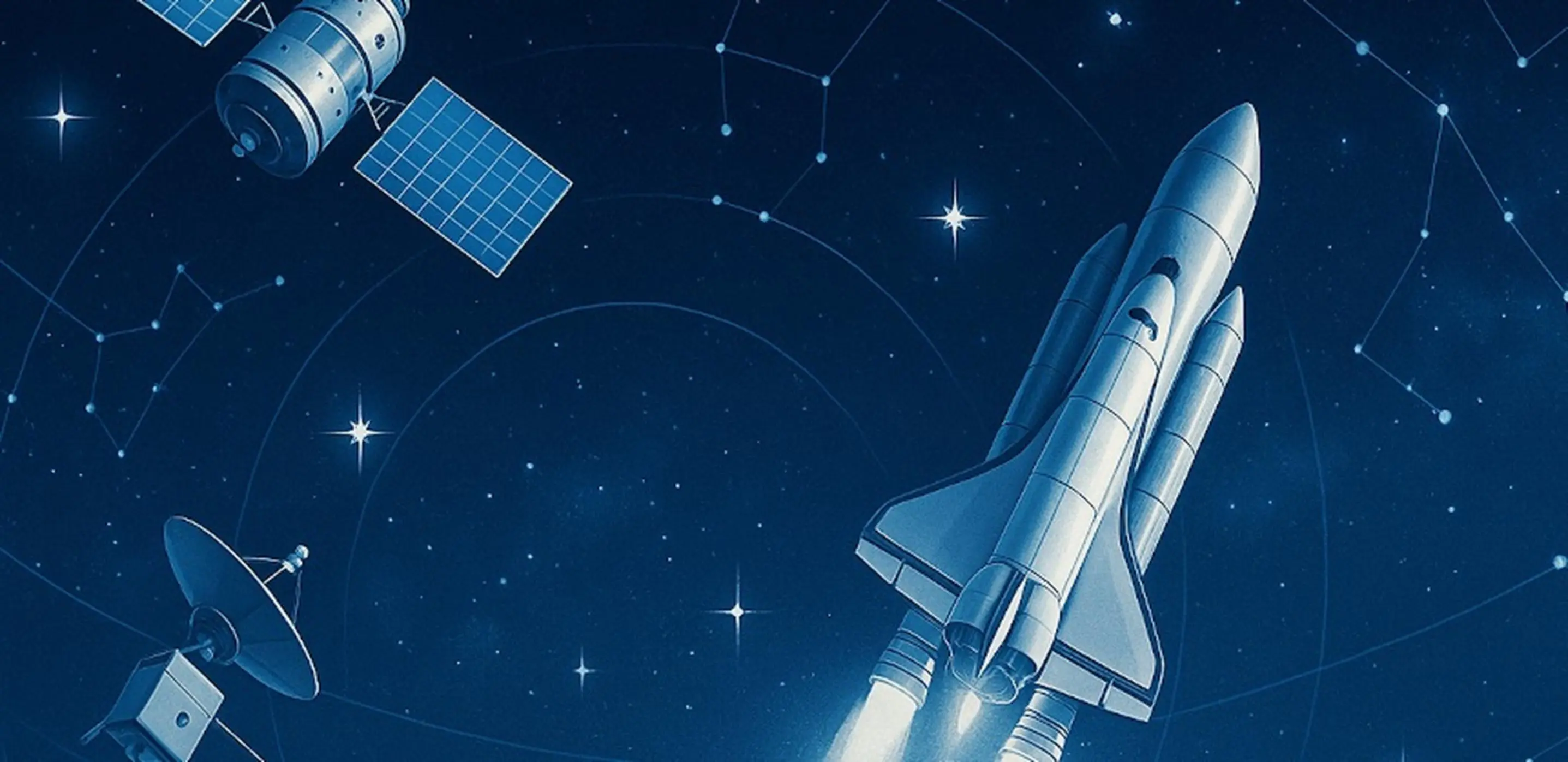はやぶさ2 とは?
- よみがな: はやぶさつー
- 英語名: Hayabusa2
概要
はやぶさ2とは、小惑星リュウグウからのサンプルリターンや人工クレーター作成などの複数の世界初を成し遂げた日本の小惑星探査機である。
詳細
はやぶさ2は、2014年に打ち上げられた小惑星探査機です。
小惑星リュウグウを探査対象とし、先代「はやぶさ」の成功と教訓をもとに開発が進められました。
初代はやぶさは世界初の小惑星からのサンプルリターンを達成しましたが、機器の故障や通信途絶など数々の困難に直面しました。
はやぶさ2では、これらの課題を克服するために、着陸精度の向上や耐久性の強化、複数の着陸機構の搭載など、技術的な改良が施されました。
観測対象である小惑星リュウグウは直径約900メートルのC型小惑星です。
水や有機物を含む可能性があることから、太陽系の起源や生命の材料に関する重要な情報を持っていると考えられていました。
はやぶさ2は2018年にリュウグウへ到達し、2度の着陸と試料採取を実施しました。
着陸には高度な自律制御技術が用いられ、探査機は自らの位置を把握しながら慎重に降下しました。
1回目の着陸では表面の物質を採取し、2回目では人工的に作られたクレーターの内部からより深い層の物質を採取することに成功しました。
ちなみに、衝突装置を用いた人工クレーターの生成は世界初の快挙でした。
これは、爆薬を使って小惑星の表面に衝突体を打ち込み、地下の物質を露出させるという画期的な試みでした。
この技術により、宇宙空間での地質調査の新たな可能性が開かれました。
様々な観測を行った上で、2020年には地球へサンプルを持ち帰ることに成功し、ミッションは大成功を収めました。
オーストラリアの砂漠に着地したカプセルには、リュウグウ由来の微粒子が多数含まれていました。
これらは現在も世界中の研究機関で分析が進められています。
初期の分析では、有機化合物や水を含む鉱物が確認され、太陽系初期の環境や生命の起源に関する貴重な手がかりが得られました。
なお、はやぶさ2は地球帰還後も拡張ミッションとして新たな小惑星探査が継続されています。
次なる目標として、2026年に小惑星トリフネへのフライバイ探査が予定されています。
また、その後は2030年に小惑星1998 KY26への接近が計画されています。
この天体は非常に小さく高速で自転しているため、探査にはさらなる技術的挑戦が求められることになります。
はやぶさ2の成果は、宇宙探査技術の進展とともに、太陽系の成り立ちや生命起源の研究にも寄与するものと期待されています。
日本の宇宙開発技術の高さを世界に示すとともに、国際的な科学協力の一端を担うプロジェクトとして、今後の宇宙探査の方向性にも大きな影響を与えるでしょう。
もっと宇宙開発について知りたい方は、
以下の関連用語についてもチェックしましょう!
関連用語・トピック
他カテゴリの用語を見てみる
人気のページ
宇宙開発ナビ:宇宙開発をこれから学ぶ人たちへ
宇宙開発について初めて学ぶならまずはこのページから。
宇宙開発ナビ:宇宙開発のメリット・デメリット とは?
宇宙開発のメリットとデメリットについて、それぞれ整理して比較します。
宇宙開発ナビ:大気圏に物体が突入すると燃えるのはなぜ?
隕石や宇宙船が大気圏に突入する際に燃えるように見える理由について説明します。
宇宙開発ナビ:太陽フレアの影響 とは?
地球にも様々な影響を及ぼす太陽フレアについて、その原因から対策まで説明します。
宇宙開発ナビ:フライバイとスイングバイの違い とは?
宇宙開発のメリットとデメリットについて、それぞれ整理して比較します。
宇宙開発用語集:通信遅延 とは?
宇宙開発を行う上で避けては通れない「通信遅延」について、詳しく解説します。
宇宙開発用語集:打ち上げ失敗 とは?
ロケット打ち上げ中に発生するトラブルとその影響について紹介します。
宇宙開発用語集:軌道の用語一覧
「軌道」という宇宙特有の考え方について、わかりやすく説明しています